パイロットが2名いる理由
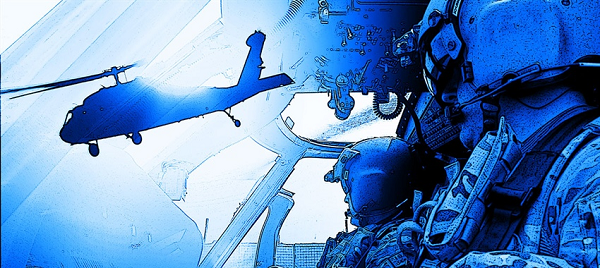
イラクに派遣されていた私は、ディーワーニーヤのFOB(forward operating base, 前方運用基地)-Eにおいて、ある患者後送中隊の一員としてUH-60を操縦していました。その中隊の主たる任務は、FOB-Eからバクダードやバラドへの患者空輸でした。その夜も、2機のブラックホークで構成される編隊の1機として、バクダードでより高度な治療を受ける1人の患者を空輸しようとしていました。その時、自分たちの命を奪いかねないような事態が起こることは、想像もしていませんでした。
天候および整備状況をチェックし、問題がないことを確認しました。機体に不具合はなく、気象も基本的に良好でした。ただし、夕方(到着時刻よりも、かなり遅い時間)に弱い砂塵嵐が発生し、重大な視程障害が生じると予想されていました。それが任務に影響を及ぼすものではないと考えた我々は、通常どおりに任務を開始しました。
バクダードまでの飛行では、特に何も起こりませんでした。半月に照らされた、明るく晴れわたった夜でした。病院で患者を卸下すると、FARP(forward arming and refueling point, 燃料弾薬再補給点)で燃料を補給し、FOBに向けて離陸しました。
夜間のイラクでの飛行を経験した者であれば誰でも知っているとおり、特に月照度が低い場合は、街から離れ、その地上の光が見えなくなると、突然、砂漠が暗黒の広大な海になり、補助目標がほとんど確認できなくなります。それから起こったことは、「マーフィーの法則」そのものでした。予報よりも2時間早く砂塵嵐が始まり、5~6マイル(約8~10キロメートル)あった視程が約1.5マイル(約2.4キロメートル)まで悪化したのです。
機編隊の2番機の機長であった私の副操縦士は、経験豊富な教官操縦士でした。私も、副操縦士も、この任務を数えきれないくらい経験しており、その経路は完全に頭に入っていました。FARPを離脱すると、ディーワーニーヤに向けて左旋回を行いました。旋回を行っている間に、僚機であった我々は、編隊の内側から外側に位置を変更しようとしていました。
その時、いくつかの事象が発生しました。まず、長機の速度計に不具合が発生し、110ノットまで機速が落ちたにもかかわらず、135ノットを表示しました(長機は、120ノットの速度を維持しようと意図していました)。長機より内側を旋回していた私の機体は、急減速することを余儀なくされました。長機が低速で飛行を続けたため、上昇して衝突を避ける必要がありました。私たちは、長機を交代して編隊の先頭に位置し、無線で調整しつつ、編隊飛行の体制を整えなおそうとしました。
計画された高度になるように上昇率を修正した時、突然、副操縦士が空間識失調に陥りました。機体は、15~20度の左バンク状態となり、毎分約400フィート(毎秒約2メートル)の降下率で高度を失ってゆきました。操縦を代わった私は、上昇を始めました。ロールを戻した時、今度は副操縦士が、私の機体姿勢がおかしいと言い出しました。
計器を見ると、降下しながら右に旋回しており、毎秒500フィート(毎秒約2.5メートル)の降下率で、機首を砂漠に向けていました。もう一度、副操縦士に操縦を交代すると、水平直進飛行に戻ることができました。もう1機が後方に続行したのを確認した後、視程障害が続く中、基地に向けて飛行を継続しました。途中のある地点では、4ローター分の距離を確保していた後続機が、我々の後部ポジション・ライトを見失うほどでした。ディーワーニーヤに到着した我々全員が認識したのは、いつもどおりの単純な任務で、事故を起こす寸前だったということでした。
その後、同種事案の再発を防止するため、部隊会同が開催され、我々の任務終了後報告を全隊員に聞いてもらうことになりました。色々な観点から議論が行われましたが、その主体となったのは、技量、経験および地位にかかわらず、誰でも空間識失調に陥る可能性があると言うことです。陸軍機は、2名のパイロットが搭乗するように設計されています。その理由は、よく言われるような「パワー・レバーの取付位置の関係で1人では操作ができない」などということではありません。陸軍のパイロットは、過酷な環境で複雑な任務を遂行しなければならないからなのです。そういった環境でそういった任務を遂行するためには、2人の操縦士がお互いに有能な副操縦士として機能することが不可欠なのです。
出典:Risk Management, U.S. Army Combat Readiness Center 2019年04月
翻訳:影本賢治, アビエーション・アセット管理人
備考:本記事の翻訳・掲載については、出典元の承認を得ています。
アクセス回数:4,062
コメント投稿フォーム
3件のコメント
平成最後の投稿です。
「2人の操縦士がお互いに有能な副操縦士として機能することが不可欠」というこの事例から得られた教訓は、航空機の操縦だけではなく、整備にも、通信にも、管制にも、そして航空以外のすべての分野にあてはまることなのかも知れません。
ぃ身がわからない笑笑笑笑笑笑笑
漢字多い
コメントありがとうございます。
これからも、「うんこ」には意味が分からないような、高いレベルの記事を提供し続けます。